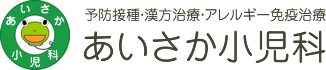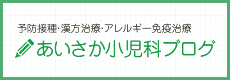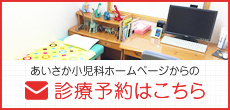成人男性の風しん抗体検査・予防接種について
実は、昨年から風しんが再流行する兆しを見せています。もし妊娠初期の女性が風しんにかかると、赤ちゃんに先天性風しん症候群という病気が発生することがありますが、この病気の発生数は風しんの流行と明らかに一致するのです。
これを防ぐためには、妊婦さんが風しんにかからないようにすることが重要で、妊娠出産年齢の女性及び妊婦の周囲から、かかりやすい人たち(風しんにかかったことがなく、ワクチンを打ったこともない方)を減少させる必要があります。
残念なことに、1962年(昭和37年)4月2日~1979年(昭和54年)4月1日生まれの男性は予防接種を受ける機会が無かったので、抗体保有率が低いのです。
つまり、現在妊娠する可能性のある女性のパートナーの男性は、抗体がない上に風しんにかかったことがない方が多い=風しんにかかる恐れのある方が多いということになります。
感染拡大を防止するためには、まずこれらの30~50 代の男性に蓄積した風しんにかかりやすい人たちを早急に減少させる必要があります。
このため厚生労働省は、これまで風疹の定期接種を受ける機会がなかった昭和37(1962)年4 月2 日~昭和54(1979)年4 月1 日生まれの男性(現在40 歳2 か月~57 歳2 か月)を対象に、風疹の抗体検査を行い、抗体価の低い人には風疹ワクチンを定期接種として行うことを発表しました。費用はかかりません(無料)。
当院でも抗体検査、予防接種に協力しています。
ご希望の方は、通常診療の予約で結構ですので、書類をご記入の上、クーポン、居住地の分かる物(免許証など)をご持参の上、来院して下さい。
おねしょについて思うこと
最近、夜尿症(おねしょ)で治療をさせていただく方が増えました。
印象としては、ホームページをリニューアルして、おねしょに関する記事をのせてから、患者さんがどっと増えたという感じです。
おねしょを発症される方が急に増えるということはないので、おそらくご家庭の中で“治る時”がくるのをひたすら待っておられた患者さんが、記事を目にされたり、ウワサを聞かれたりして本院を受診されるようになったのだと思います。
おねしょは小学校1年生では、約10%のお子さんにみられるので、1クラスに3人程度はいることになり、実はかなり困っておられる方がおられます。おねしょ(夜尿症)があると、自分自身を評価する気持ち(自信)が、一般的に低くなりやすく、学校での活動性、学業などにネガティブな影響が出ることがあるといわれています。
しかし治療を行うと、自然に治るよりもずっと早く治せることもわかっています。
実際、患者さんにキチンと夜尿のメカニズム、生活改善のポイントをお話しすると、それだけで“治った!”と言われることもあります。また、夜尿の原因を正しく推定して薬剤による治療を行うと、自然に放置した場合に比べて1年後には、約4倍多く治ることがわかっています。
“治った”と言ってもらえたとき、子どもさんが本当にうれしそうな顔をしてくれるのを実感できるのが、夜尿の診療を行っていてやりがいを感じる点です。
もし、この記事を読んでご興味をもたれたら、一度相談されることをお勧めします。最初の受診はご家族だけでもかまいません。
今年も噛まれました

アレルギー免疫療法について
免疫療法について
先日の研究会で、免疫療法の最新の治療成績や知見について勉強してきました。自分の知識の整理のためにも、免疫療法について少しまとめておこうと思います。
一般的なアレルギーに対する治療薬は、抗アレルギー剤と言われる物が中心で、症状を緩和するために服用しますが、アレルギーそのものを治す事はできません。
これに対して免疫療法を適切に行うと、
-
① 治療効果が長期間持続し、今まで使っていた薬を減らしたり、生活の質を向上させることが期待できます。
-
② また今後、他のアレルギーが起きることを抑制できる事が、報告されています。
-
③ 小児でダニアレルギーによる鼻炎があると、今後喘息を発症するリスクが高まりますが、免疫療法を行うことで喘息の発症頻度を抑制できることが、報告されています。
-
-
というわけで、今までの治療は “その場をしのぎ” (語弊があるかもしれませんが・・)であるとすれば、免疫療法は“根治”や“他のアレルギーの発症予防”が期待できる治療であるといえます。アレルギー性鼻炎の治療ガイドラインでも、症状の軽い重いを問わず実施できることになっています。
-
現在、免疫療法にはスギ花粉症とダニアレルギーに対する治療薬があります。最近になって適応年齢が引き下げられ、小学校低学年くらいの子どもさんから実施できるようになっています。一般的に、若年者の方が得られる効果が高いといわれていますので、他のアレルギーを予防する点からも、子どもさんにお勧めできる治療だと思います。もちろん健康保険が適応しますので、普通のカゼと同じような自己負担の範囲で治療ができます。
-
ただし、“体質”を変えてアレルギーを治すわけですから、短期間では効果は出ません。
WHOの見解では3~5年を目安に、自己判断で中断せずに行うこととなっています。
うちのクリニックでも免疫療法のメリットと、長期にわたり治療を継続する心構えが必要であることを説明してから治療を行っています。
-
ともあれ、今までのアレルギーの治療薬が、その場の症状を抑える対症療法であったことから考えると、長期にわたり症状を緩和し、新たなアレルギーの発生を予防できる免疫療法は、今後のアレルギー診療において、ますます普及していく治療法であることは間違いないと思います。
発熱と熱中症について
今年はまれに見る酷暑ですね。
ニュースでは毎日のように熱中症による救急事例が報道されています。
クリニックでも、高熱でぐったりした患者さんが来院されると、
熱中症でしょうか?という質問をよく受けています。
でも、そのほとんどは夏風邪などの感染症です。
そこで、今回は熱中症について正しい知識をおさらいしてみましょう。
熱中症とは
高温環境下で、体内の水分や塩分(ナトリウムなど)のバランスが崩れたり、
体内の調整機能が破綻したりして、発症する障害のことです
そしてその症状は 軽いものから順番に以下のようになります。
I度
めまい・立ちくらみがある
筋肉の「こむら返り」がある。痛い
大量の発汗
II度
頭痛がする
気分が悪く、吐き気・嘔吐がある
しんどい
III度
呼びかけや、刺激への反応がおかしい
けいれんする
高い体温である
ということで、熱中症で高体温の状態になるのは、重症であると言うことになります。
クリニックに来院される程度の熱中症では、めまい、頭痛、倦怠感などの症状が多く、
程度もひどくないものが多いようです。
最後に、熱中症は予防が大切なことはご存じのことと思いますが、
熱中症を疑ったときの初期対応を記載しておきます。
1) 涼しい環境への移動
2) 脱衣(熱の放散を助ける)と冷却(水をかけたり、氷嚢を利用する)
3) 意識がはっきりしているようなら、水分・塩分を摂取する
以上、参考にしてください。
花いっぱいに・・


毎年、医院前の歩道の花壇に花を植えていました。
今年は何を植えようかと迷っているうちに、
職員さんが苗を買ってきて植えてくれました。
お隣の薬局さんへの歩道が、とても華やかになりました。
ウッドデッキのプランターにも花を植えました。
梅雨時期にも明るい雰囲気になりますように・・。

麻疹の流行と緊急ワクチン接種について
昨今、ニュースなどで報道されていますが、沖縄で麻疹が流行しています。特にゴールデンウィークで日本国民族大移動が起きる時期ですので、沖縄地方を越える感染拡大のおそれも出てきました。
このような状況で、沖縄への旅行や、定期接種の時期(1才児、いわゆる年長さん相当児)以外でのワクチン接種についてのお問い合わせが増えてきましたので、Q&Aでお答えしておきます。
Q ① 1才未満でも麻疹ワクチンは接種できますか?
A 生後6ヶ月以上になれば、麻疹の流行時期には接種が可能です。ただし、この場合の接種は自費
になります。また生後1才を過ぎたら、定期接種として、通常の通り2回の定期接種を受ける
必要があり、計3回の接種を受けることになります。
Q ② 今までに1回だけワクチン接種をうけていますが、大丈夫でしょうか?
A 感染予防に十分な抗体を獲得するためには2回接種が必要です。50才以下で今までに1回しか
麻疹ワクチンを受けたことがない方は、感染予防のためワクチンを接種された方がよいと思い
ます。
Q ③ 1才で1回ワクチン接種を受け、年長さんの年齢になっていません。この場合は接種した方がい
いでしょうか?
A しらべた範囲で、明確な指針は見つからなかったのですが、このような方が沖縄への旅行を計画さ
れている場合などは、接種したほうがいいのではないかと考えます。この場合も接種は自費にな
ります。
ウッドデッキを再塗装しました
早春の気配が漂うようになり、
天気のよい日が続いたので、
ずっと気になっていた、日焼けしたウッドデッキの塗装をしました。
塗装前と塗装後です


素人仕事ながら、だいぶん見栄えがよくなりました。たぶん。
子どもたちへのごほうび

うちの職員手作りの折り紙トトロ
とてもよくできています。
検査や注射をがんばった子どもたちへのごほうび。
小児科学会滋賀地方会に参加してきました
去る10月14日に、小児科学会滋賀地方会に参加してきました。その日楽しみにしていたのは、滋賀医大小児科学講座の丸尾新教授による特別講演でした。丸尾教授は私とは滋賀医大の同期で、学生生活を6年間、研修医生活の3年間、計9年間を一緒に過ごしてきた仲です。
丸尾教授の研究テーマは新生児黄疸、体質性黄疸をはじめとした黄疸の研究なのですが、その講演内容の壮大なこと。びっくりしました。
黄疸の素になる物質の働きから、生物種(植物、動物)においてその化学反応に関連する酵素が解毒作用と関わっているという話や、黄疸の素になる物質は、少量なら酸化ストレスから体を守るように働いているという話、新生児期に黄疸が出るのは、もしかしたら脳神経の発達に有利に働いているのではないかということまで、まさに知的好奇心を刺激する内容でした。今後どんなふうに研究が展開するのか、新しい発見があるのかワクワクします。
自分の同期が小児科講座のトップとなり、世界からも注目される黄疸関連の研究のスペシャリストとなったことはとてもうれしいことです。日々の診療を行い、教室を運営し、次世代を担う人材を育てることなど、彼にかかる責任は大変なものだと思いますが、今後の活躍を期待し、応援したいと思っています。