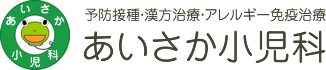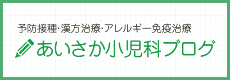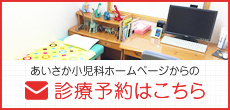5~11歳の方お子さんに新型コロナワクチンを打つかどうか迷われている方へ。
5~11歳のお子様に新型コロナワクチンを打つかどうか、迷われている保護者の方も多いと思います。
ここでは、発表されている事実をご紹介しつつ、私見も交えてワクチンを接種する・しないの判断の材料にしていただける記事を書きましたので、ご一読ください。
まず5~11歳の小児に使用できるワクチンは、ファイザー社製になります。
以下はワクチンの海外で5~11歳の小児へのワクチン投与治験で得られたデータです。(日本では同様の治験は行われていませんが、様々な検討からワクチンの効果に人種差は認められず、日本の小児にも同様の効果が期待できるとされています。)
効果については以下の通りです。
このワクチンを2回接種して1ヶ月経過してからコロナウイルスに対する中和抗体を測定すると、プラセボ(本物の薬と見分けがつかないが有効成分が入っていないもの)と比べて100倍以上の差を持って上昇が認められました。
これは他の年齢の抗体価の上昇と同じ程度でした。つまり、小児だからワクチンの効果が薄いということはなさそうです。
副反応について
発赤、腫脹、疼痛、発熱、疲労、頭痛、悪寒などが多く、他の年齢と比べて大きな差はありません。また、その程度も軽症から中等度のものがほとんどで、副反応による死亡の報告はありませんでした。
従来危惧されていた心筋炎・心膜炎の発生は、実際にコロナに罹患して合併する心筋炎・心膜炎の頻度よりも低く、発生したとしても、その程度は軽かったと報告されています。
これらをふまえて、小児科学会では
新型コロナワクチンを5~11歳の小児に接種する事について、以下のような提言を行っています。
①5~11歳の健康な子どもへのワクチン接種は12歳以上の健康な子どもへのワクチン接種と同様に意義があると考えています。
②2歳未満(0~1歳)と基礎疾患のある小児患者において重症化リスクが増大することが報告されています。
③基礎疾患のある子どもへのワクチン接種により、COVID-19の重症化を防ぐことが期待されます。(ワクチン接種を考慮した方がよい基礎疾患とその状態についてはこちらを参照)
④基礎疾患を有する子どもへのワクチン接種については、本人の健康状況をよく把握している主治医と養育者との間で、接種後の体調管理等を事前に相談することが望ましいと考えます。
以下は私見を交えてのまとめです。
現状小児のコロナ患者が重症化する例はかなり少ないと思われるので、ワクチンを接種しないという養育者の選択を否定する物ではありません。
ただし、小児がコロナに罹患することで、同居されている乳幼児、高齢者、基礎疾患がある方などへの影響を心配される場合、保護者の方の仕事の関係で、出来るだけ新型コロナにかかるリスクを減らしたいと思われる場合には、接種するメリットがあると思われます。
要するに、健康な子どもへのワクチン接種には、メリット(発症予防等)とデメリット(副反応等)を本人と養育者が十分理解し、十分に相談の上で接種をするかどうかを決めて頂くのがよいと思われます。
子宮頸がんワクチンの疑問に答えます
子宮頸がんワクチン(HPVワクチン)が小学校6年生~高校1年生の女の子に対して定期接種になっていて、公費(無料)で接種を受けられることをご存じですか?
実は2013年から定期接種となっていていたのですが、一時期、接種後の体の痛みなどを訴えるケースが出たため、その後積極的に勧奨しない(お勧めしない)という、あいまいな立場のワクチンになっていました。
その後の検討で、接種と無関係に原因不明の痛みを訴えるケースが一定数あることから、ワクチンと副反応の因果関係は否定されました。しかし、一度信頼を失ったHPVワクチンの接種は進まないままになっていました。
世界に目を向けると、HPVワクチンは世界100か国以上で導入されています。また、昨年発表されたカロリンスカ研究所(ノーベル賞で有名ですね)の論文では、接種を行った女性の場合、子宮頸がん発症のリスクが63%低下したことが報告されています。日本ではワクチンをうたないまま10年近くが経過したため、この間に先進国では子宮頸がんの罹患率、死亡率ともに減っているのに、日本では増加しているという結果もでています。
子宮頸がんの罹患率は20代後半にピークになり、40歳前後までが高いことが知られています。結婚、妊娠、出産、子育てをする年齢の女性に多いがんなのです。しかし、ワクチンによって予防できる数少ないがんであることを強調しておきたいと思います。
HPVワクチン接種後の副反応として重篤な副反応が起こる割合は低く、厚生労働省のデータでは2,000人のうち1人という割合です。ただ、副反応で苦しんでいる方がいることや、リスクがゼロではないことも事実です。しかし、ワクチンを打って副反応が起きるリスクよりも、打つことで命に関わる病気を予防できるメリットの方がはるかに大きいといえます。
産婦人科学会も小児科学会も、科学的な根拠に基づいて接種をおすすめしていますが、それでも接種に関する心配があるようでしたら、遠慮なくご相談いただくのがよいと思います。
便秘について 最終回
さて、子供の便秘についてのブログも今回が最後です。
初めてこのブログに来られた方は、ここから読んでいただいてもけっこうです。今回は過去5回分のまとめになります。
まず、便秘治療の3大原則は以下のことになります。
① 便秘治療の最初にやることは、おしりをフタしている便塞栓(硬い便の塊)があるときは、便塞栓を除去してから、薬、食事、生活改善などの他の治療を開始する。
② おしりのフタが外れたら、そのままにしておくこと。また硬い便でおしりにフタができないようにする。
③ おしりにおりてきたうんちは、我慢しないで出し切る習慣を身に付ける。
実際の診療の場面でよく陥る間違いもあげておきます。
便塞栓の除去では、浣腸を1回して便が出たら、それでOKと思ってしまう。 → 実際には、まだ腸の中に便がたまっていることが多いです。
→ 内服を開始しても、硬い便が出るときは、また浣腸が必要です。
内服薬を途中でやめてしまう。
→ 内服でいい便が出るようになったら、それを継続しましょう。
→ 毎日排便があっても、硬い便が出ているようなら、まだ便秘です。
→ 便通の経過を報告して、薬をやめる時期を一緒に考えましょう。
排便は本人にまかせっきり
→ 年齢により、排便のメカニズムは異なります。年齢に応じた排便習慣があり、適切な便の硬さになっているか確認しましょう
→ 排便イヤイヤ期(排便恐怖や遊びに夢中、パンツ移行期など)は誰にもあります。少しずつでも出来るようになったことをほめて、生活習慣として関わってあげて下さい。
今回の学会のセミナーを通して、便秘の治療は私自身が思う以上に長期戦であることを再認識しました。でも、便秘を正しく認識して、治療を継続しようという気持ちと、正しい治療を組み合わせることで、便秘による苦痛や“排便恐怖”からお子さんを解放してあげることが出来ます。
排便について気になることがあるようでしたら、まずはご相談いただけたらと思います。
便秘についてはこれでおしまいです。
お子さんの毎日が、「すっきりうんこで今日もニコニコ」になりますように。
便秘について その5
今回は便秘についての5回目、治療のゴールについてです。
便秘の治療の流れをもう一度整理しておきましょう。
第一段階 おしりをフタしている便の除去(便塞栓の除去)
第二段階 苦痛なく排便できるようにする(薬で補助)
第三段階 ため込まない排便習慣を確立する(薬で補助)
第四段階 服薬中止
さて、便秘の治療にかかわっていると、薬についてよくお聞きする質問に以下のようなものがあります。
① 便が出たら薬はやめていいですか?
② いつまで飲み続けるのですか?
③ 薬はくせになりませんか?
① については、くどいようですが、1回排便があっても慢性の便秘の場合、まだ直腸内に便がたまっていることがあります。また、おしりをフタしていた便を出しても(便塞栓の除去)をしても、それは第一段階をクリアしただけです。続けて生活改善(生活習慣、食習慣、排便習慣)が身につくまで、薬で便秘にもどらないように補助し、本人の“排便恐怖”を解消していかなければなりません。
第一段階の便塞栓の除去は、浣腸によって除去すること自体は比較的短期間で達成できます。
② 便塞栓が取れたら、うんちの硬さ、回数、量を指標にしながら、生活改善(生活習慣、食習慣、排便習慣)にとりくみます。この時に薬で苦痛のない排便を補助し、第三段階の排便習慣が確立するまでは飲み続けなければなりません。
第二~三段階でお薬を利用するわけですが、便秘治療のガイドラインでは、「通常6~24か月を必要とする。」という記載があります。さらに、お薬をやめるときも、時間をかけて徐々に減量した方がいいということになっています。
③ 薬についていうと、中には習慣性のある薬もありますが、それよりも便秘がクセになり、便意を感じにくくなって、直腸に便がたまったままの状態が続くことの方が問題であるといえます。早く薬をやめたいというのであれば、便が出ても出なくても積極的にトイレトレーニングをしてみましょう。便意を感じやすくなると、早く薬をやめられるようになります。
今回の内容から薬を利用する期間は「思ったほど短期間ではない」ということをご理解いただけたでしょうか?便秘の治療は、出たらよい、出せればよいというような、単純なことではないのですね。
今回は以上です。次回は便秘の最終回、まとめになります。
便秘について その4
便秘についてその4です
さて、便秘の治療では、
① 一旦固くなってたまっている便を浣腸などで除去して、空っぽにする。
② そのあと規則正しい生活習慣、バランスの取れた食習慣などで、排便習慣の確立を身に着けるようすること。
③ 内服薬はこの習慣が確立するまでの補助である。
ということを書きました。
排便習慣が確立するということは、「普段は直腸が空っぽで、直腸にうんちがおりてきたら排便して、また空っぽにする。」といことが出来るようになることを言います。繰り返しになりますが毎日排便があっても、直腸にたまった便が少量ずつ出ているだけで、空っぽになっていないようなら、まだダメなのです。
食事については、水分量や繊維質の食品などを摂取した方がよさそうですが、便秘と唯一関連があったのは食事中の脂肪の割合で、これが高い場合は便秘になりやすい傾向が認められたそうです。つまり便秘であっても、普通にバランスの取れた食品の摂取をおこなっていればそれでよいということの様です。
便塞栓の除去については、現状では浣腸が唯一の治療方法になります。方法としてはグリセリン液を用いた浣腸を1日1回、3~6日間継続することが推奨されています。
その後、排便習慣が確立するまでお薬を使うわけですが、従来のお薬の中には、腸管を刺激して便意を出すものがあります。このような薬を使う場合は、便塞栓を完全に取っておかないと、便意を催しても腹痛が起こるだけで、排便の恐怖心のみを残すことになりかねません。
最近になって、腸管への刺激作用が少ないお薬も出てきました。ただし、刺激作用が少ないということは、便意を自覚しにくいということが弱点になります。そこで、積極的に排便を促してあげる働きかけが重要になります。(トイレトレーニングのできる年齢以降)
具体的には
便意がなくても排便がなかった日は、夜にトイレで排便努力してみる
朝晩の食後にはトイレに行く時間を作って、排便努力してみる
ということです。
ただし、トイレトレーニングには正しい排便姿勢があります。
どういうことかというと、足は床について、踏ん張れるようにしてあげることが大切です。一般の便器に補助便座を置いて座らせる場合は、足台も置いてあげてほしいのです。また、いきむときには少し前かがみになることが必要で、前から手をつないであげたり、ハンドル付きの便座やオマルを利用するのがいいと思います。
そして子どもの努力をほめてあげる声かけをしてあげてください。
慢性便秘のお子さんの場合、トイレトレーニングは遅れがちになりますが、治療の一環としては非常重要で、これをきっかけによくなることがあります。
今回はここまでです。
便秘について その3
少し秋めいた気配が感じられるようになってきました。さて、小児の便秘についての第3回です。今回は、便秘で悩むお子さんや、親のよくある気持ちについて書いてみます。
まず、親御さんの声
(学会で紹介されていた内容)
① 便秘はしつけの問題ではないかといわれた
② 相談できる相手がいない
③ ついつい子供を叱ってしまう
④ かかりつけの小児科で相談すると浣腸だけでおしまいになった
(ここから下は、私の経験から)
⑤ 排便で苦痛があったり、おしりが切れたりするのがかわいそう
⑥ 内服を勧められたが、結局うまくいかなくてあきらめた
⑦ 薬に頼るとクセになって、薬をやめられなくなるのではないか心配
少し大きい子どもさんの気持ち
(学会で紹介されていた内容)
① まわりから臭いといわれる
② 授業中にトイレに行きたいといえない
③ はずかしい
(ここから下は、私の経験から)
④ トイレトレーニングが嫌
⑤ いつも決まった場所、慣れた場所で排便したい
⑥ もよおしても、排便が嫌なのでがまんしてしまう
⑦ 浣腸や、診察の時にものすごく怖い経験をした
(こんなこともあるのかと納得した話)
⑧ 水洗トイレの音が怖い
⑨ トイレの跳ね返りの水がくっついたことがあって嫌になった
子どもさんならではの気持ちもあるのですね
あるあるだった?でしょうか??
新型コロナウイルスワクチンその3
・健康な子どもへのワクチン接種
接種によるメリット(感染拡大予防等)とデメリット(副反応 等)を本人と養育者が十分理解し、接種前・中・後にきめ細やかな対応が必要です。
日本小児科学会では、12歳以上の健康な子どもへのワクチン接種は意義があると考えています。新型コロナウイルス感染予防対策の影響で子どもたちの生活は様々な制限を受け、子どもたちの心身の健康に大きな影響を与え続けています。小児患者の多くは軽症ですが、まれながら重症化することがありますし、同居する高齢者の方がいる場合には感染を広げる可能性もあるからです。
参考サイト 「新型コロナワクチン~子どもならびに子どもに接する成人への接種に対する考え方~」に関するQ&A
うちの子ども(12歳以上)は健康ですが、ワクチンを受ける意義はあるのでしょうか。
すでに書いたように、国外での小児を対象としたワクチン接種経験等では、接種後の発熱や接種部位の疼痛等の副反応出現頻度が比較的高いことが報告されています。そこで、子どもへのワクチン接種は、まず、子どもに接する成人への接種を充実したうえで慎重に実施されることが望ましく、接種にあたってはメリットとデメリットを本人と養育者が十分に理解していること、接種前・中・後におけるきめ細かな対応を行うことが前提になります。
参考サイト 「新型コロナワクチン~子どもならびに子どもに接する成人への接種に対する考え方~」に関するQ&A
新型コロナウイルスワクチンその2
・重篤な基礎疾患のある子どもへの接種
ワクチン接種により新型コロナウイルス感染症の重症化を防ぐことが期待されます。
国外では神経疾患、慢性呼吸器疾患、免疫不全症を有する子どもの感染例で重症化が報告されています。これをうけて、国内でも基礎疾患のある子どもの場合、ワクチン接種によって重症化を防ぐことが期待されると考えています。
重症化リスクが高いといわれる基礎疾患には次のようなものがあります。神経疾患、脳性麻痺、慢性肺疾患、慢性心疾患、ダウン症候群をはじめとした染色体異常症、悪性腫瘍や移植などによる免疫不全状態、高度肥満など
参考サイト 「新型コロナワクチン~子どもならびに子どもに接する成人への接種に対する考え方~」に関するQ&A
うちの子ども(12歳以上)には持病があって定期的に通院しています。うちの子ども(12歳以上)の持病は新型コロナワクチンの優先接種対象の「基礎疾患」に該当するでしょうか。
ただし、思春期の子どもや若年成人では、接種部位の疼痛出現頻度が約90%と高く、特に2回目接種後に発熱、全身倦怠感、頭痛等の全身反応が起こる頻度が高いようです。基礎疾患を有する子どもへのワクチン接種については、本人の健康状況をよく把握している主治医と養育者との間で十分な接種前の説明を行い、接種後の体調管理等を事前に相談することが望ましいとしています。
新型コロナウイルスワクチンについて
基本的な考え方
・子どもを新型コロナウイルス感染から守るためには、周囲の成人(子どもに関わる業務従事者等)への新型コロナワクチン(以下、ワクチン)接種が重要です。
これは、子どもへの感染源の多くは周りにいる成人だからです。
つまり、コロナウイルス感染で重症化するおそれのある基礎疾患をもつ子どもに関わる業務従事者はもちろん、健康な子供に関わる業務従事者も、職種・勤務形態を問わずワクチンを接種することが重要との考えを示しています。
便秘について その2
さて、今回は小児の便秘の2回目です。
便秘の起きやすい時期と、排便・便秘のメカニズム、治療の原則について書きます。
まず便秘の起きやすい時期からです。
生後すぐの新生児期からの便秘
このような時期から起きるものは、むしろ外科的な治療が必要な重篤な疾患である可能性が高いです。
乳児期における食事の移行期
この時期の赤ちゃんは、まだ自分の意志でおしりを緩めて、いきんで排便するという一連の協調した運動ができません。また、離乳食により便が次第に“形”として固まってくるため、自力で排便しにくくなることがあります。なので、この時期は単純に便を柔らかくすることで便秘が改善することが多いようです。
幼児におけるトイレットトレーニング期
この時期になるとは、自分の意志でおしりを緩めて、いきんで排便するというトイレトレーニングが出来るようになってきています。しかし、逆に言うと、自分の意志で排便を我慢することもできるようになっています。このため、何らかの原因で排便が苦痛であるという経験をすると、それ以降に“うんちをするのが怖い”という考えに支配されるようになってしまいます。このような場合は、“うんちをするのが怖い”という思考を変えてあげるようにしないといけません。
学童における通学の開始期
この時期は、幼児期から大きくライフスタイルが変化します。排泄に関して言うと、“自由にトイレに行けない”ような生活に変わっていくわけです。このため、朝の排便の時間が十分とれない、便意を催しても、授業中は我慢しないといけない、などの問題が出てきます。また男の子の場合、排便への羞恥心などもでてくるようになります。この時期には個々の問題について、解決をはかる必要が出てきます。
ここで排便のメカニズムについて説明します。
大腸で次第に形ができた便が直腸をおしひろげると、脳に便がおりてきたという情報が伝わります。そうすると、排便が可能になる時期までは、自分で外肛門括約筋をしめて便を我慢します。そのあとトイレに行くと、括約筋を緩めて、おなかに力を入れて排便します。これとは別に食事をした時は、胃の中に食事が入ったという刺激で胃結腸反射というものが起きて、腸がぐるぐる動いて排便につながります。
便秘の子の場合、慢性的に直腸に便がたまっており、便意を感じにくくなっています。便秘が進むと、食欲も落ちてくるようになり、胃結腸反射による腸のぜん動運動も落ちてきます。そうして便秘が成立してしまいます。
また、一旦便秘になると、
① 排便時に痛い→②排便我慢→③便塞栓→④水分が抜けて硬くなる
この①~④の悪循環におちいってしまいます。また、この時は体の便意を感じるセンサーや反射も鈍っていくので、さらに便秘はひどくなっていきます。
便秘の治療においては、まず硬くつまっている便(便塞栓)を除去して便が通りやすくなるようにしなければいけません。便秘の悪循環を断つためにもこれは重要なことです。ただし、一旦固くなってたまっている便を内服薬で柔らかくすることは困難です。そこでまず、浣腸などで便塞栓を除去することが最初に必要なことです。
そのあとから、規則正しい生活習慣、バランスの取れた食習慣、排便習慣の確立を身に着けるようにしていきます。内服薬はこの習慣が確立するまでの補助です。内服薬だけで生活改善なく便秘が治っていくことは困難なのです。
今日はここまで。お子さんやお母さんの気持ちや、治療については次回書きます。